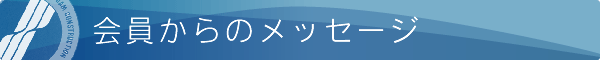
「ダム工事との関わり」 第27期 加納 清(鹿島建設)(2010/08/21)
 私は入社してからはしばらく、設計業務、都市土木の現場に従事し、ダムとは全く違う工事を担当しておりました。その後、入社4年目で結婚しました。その結婚披露宴の席での話です。部長にスピーチをお願いしていた関係上、やはりスピーチの話題は建設業界や仕事の話が中心となっておりました。スピーチの半分ぐらいのところで、「次はダム工事へ行ってもらいます。」と突然の一言、全く予想もしていなかったため、少し驚きと不安がありました。その言葉通りにロックフィルダムの現場へ配属となり、最初は右も左も分からず、ダムの盛立は当然見たこともなく、洪水吐、監査廊工事と言われてもどのように施工していくのか、全くイメージが持てませんでした。今思えば、ここからダム工事との関わりができ、現在に至ったのだと実感しております。
私は入社してからはしばらく、設計業務、都市土木の現場に従事し、ダムとは全く違う工事を担当しておりました。その後、入社4年目で結婚しました。その結婚披露宴の席での話です。部長にスピーチをお願いしていた関係上、やはりスピーチの話題は建設業界や仕事の話が中心となっておりました。スピーチの半分ぐらいのところで、「次はダム工事へ行ってもらいます。」と突然の一言、全く予想もしていなかったため、少し驚きと不安がありました。その言葉通りにロックフィルダムの現場へ配属となり、最初は右も左も分からず、ダムの盛立は当然見たこともなく、洪水吐、監査廊工事と言われてもどのように施工していくのか、全くイメージが持てませんでした。今思えば、ここからダム工事との関わりができ、現在に至ったのだと実感しております。
私のダム工事経歴ですが、初めてのダム現場は福岡県の山口調整池、その後、宮崎県の小丸川発電所上部ダム、大分県の稲葉ダム、現在施工中の鳥取県の殿ダム、計4つのダム工事を担当、主にロックフィルダムの施工に従事してきました。その中から、最も長期間に渡り施工してきました小丸川発電所上部ダム工事について少し書きたいと思います。
小丸川発電所は、宮崎県児湯郡木城町(宮崎県のほぼ中央)に位置し、2つのダムを持つ純揚水式発電所です。そのうちの上部ダムは、アスファルト表面遮水壁型ロックフィルダムで、貯水池全面をアスファルト遮水壁で覆う工法が採用されております。舗設面積は、約30万m2で我が国最大規模の面積を誇ります。
宮崎県といえば、昔は新婚旅行の代表的な場所。現在ではプロ野球やサッカーのキャンプ地、またゴルフ関連では「ダンロップフェニックス」の開催地としてよく知られており、南国でとても温暖なイメージが定着しているかと思います。しかしながら、小丸川発電所の上部ダムが建設された場所は標高800mと高地で、冬季は雪が降ることが何度かありました。また、朝礼時でも氷点下5〜6℃と非常に寒く、自分の中では南国のイメージは早々に消え去ってしまったことを記憶しております。
美味しい食べ物も豊富な地域で、特に地鶏、牛肉、マンゴーなど有名食材がいつでも手に入り、たまに贅沢な気分を味わうことができたという良い思い出もあります。そんな牛肉も、最近の「口蹄疫」問題が毎日のように報道され、現場の近くで牛舎を見ていた者の一人としては、他人事とは思えず、なんとか早く被害が収まり、また元の生活が戻ってくることを願っております。
最後に、ダム事業は逆風の中で大変な時期を迎えておりますが、CMED会の会員としてダム事業の発展と社会貢献に少しでも寄与することができればと思っております。
(だよりN0.45号:会員の輪より抜粋)
「ダムとの関わり」 第21期 木全 克夫(2010/03/09)
 現在、現場を離れて既に8年ほど経ちますが、今回投稿するにあたり改めて自身とダム関わりを思い起こしてみました。
現在、現場を離れて既に8年ほど経ちますが、今回投稿するにあたり改めて自身とダム関わりを思い起こしてみました。
初めてのダムは長野県の奈良井ダムです。新入生の年に当時の上司から赴任するように言われ、当然のことながら否応もなく赴きました。そこで初めて速達配達外区域と言うところがあることを知りましたが、自然豊かで休日には他社の職員の方とも良く遊び回り、今でもたまにお会いすると懐かしくお話しをさせて頂いています。一人で夜勤番をしている時には、多くの作業員の方々や大型重機が稼働しているのを見て、自分も立派な監督さんになったもんだと誤解をしていたものです。
二つ目のダムはマレーシア(ボルネオ島)のバタンアイダムです。会社の費用で生まれて初めての海外に行けると知り、1年間手を挙げ続けようやく行かせてもらえることになりました。気候や食事、勤務環境等その当時は厳しかったとは思いますが、今思い出されるのは楽しい思い出ばかりです。また最後の1年間は、船でさらに3日ほど上流に遡るジャングルの奥地の調査現場に赴任し、異国でのジャングル生活を満喫していた思い出があります。
三つ目のダムは群馬県の大仁田ダムです。それまでしばらくダム現場を離れていた時に、飲み会の後以前のダム現場の上司に「そろそろダム現場に行きたくならないか?」といわれ、具体的な話があるとは知らずに「是非とも行かせて頂きたい」と調子よく答えたことが思い出されます。結局後日再度意思確認があった時には、後には引けず家族同伴で行くことになりました。家族は初めて大阪の地を離れ群馬県に移り住んだのですが、毎晩日付が変わってからの帰宅となり家族には迷惑をかけました。家族はその後大阪に帰りましたが、今では群馬県の生活が良かったと懐かしんでいます。またこの頃からダム独特の世界があることを知り、自分もいつかその一員になりたいと心中で密かに思い始めた頃です。また「CMED」と言う資格についても話が聞こえ始めましたが、そのあまりにも難しく期間が長い試験に対して、自分にはとても無理だとの想いで傍観していた気がします。
四つ目のダムは埼玉県の滝沢ダム原石山工事です。この頃には他社のダム屋さんとも知り合う機会が増え始め、また自分の経験や知識の総括として一度はじめから体系的にダム技術について勉強し、その結果として「CMED」を取得したいという気持ちが生まれました。幸い単身赴任をしていたこともあり、休日には何ら囚われることなく勉強をしていた記憶があります。
このように、今まで自分の意志や誰かに導かれて関わりを持ってきた私のダム現場経歴は合計で11年程度しかなく、多くのCMED会員の方から比べると非常に少ないとは思いますが、自身の会社経験や50数年の人生の中で貴重な財産であり、大きく重要な比重を占めていると思っています。
ダム技術者は他の土木屋さんと異なり、講習会や研修会、見学会、試験会場等でお会いすることが多く、社内だけに留まることなく広く社外の方々と知り合える貴重な経験が出来る素晴らしい世界です。
このような素晴らしい機会が得られる場を後輩にも経験させられるように、今後ダムを取り巻く周辺の環境が改善されればと思っています。
(だよりN0.44号:会員の輪より抜粋)
「ダムへの係わりと思い出」 第24期 木村 孝(2010/03/09)
 私が経験したダム工事は3件で、全てロックフィルダムです。
私が経験したダム工事は3件で、全てロックフィルダムです。
初めてのダム現場は臼中ダムでした。臼中ダムは富山県南西部の福光町というところにあり、石川県金沢市の東隣りという位置です。
町一番の繁華街から車で約30分、最も近い民家から車で15分のところでした。ダム工事が建設される前には集落があり、その跡地が何箇所か見られるところでした。工事中も山菜を取るため、山小屋に住まわれているご夫婦がいらっしゃいました。テレビの電波が弱く、隣接する山の頂上にアンテナが設置され、毎年春先にメンテナンスを行っていました。30年近く前のダム現場でしたから、近年のダムに比べて随分山奥であったような気がします。またこのダムでは、本体掘削岩の中に梅の化石が含まれた珍しい花崗岩がありました。大昔は梅の名所だったのかもしれません。川にはイワナが生息し、自然豊かなところでした。
臼中ダム工事の最終年度の4月に次のダム現場、蔵王ダムへ転勤することになりました。
蔵王といえば、東北の蔵王を思い浮かべられる方がほとんどだと思いますが、このダムは滋賀県の南部、三重県との県境に近く鈴鹿山脈の麓付近に位置しておりました。家々からほんの数百m、山に入った場所でした。直下流に小さな神社があり、そこを境に雨が降っていたということもありました。
仮締切の盛立が終わり、堤敷部の基礎地盤検査の準備を行っている頃、一雨雨量200mmを超える集中豪雨がありました。普段は川幅5m程の流れにもかかわらず仮排水トンネル吐口から50mほど勢いよく流出する水を見て、自然の脅威を様々と感じさせられました。
この後しばらくダム工事から離れ、(財)日本ダム協会の施工技術研究会にも参加させていただくようになりました。
それから、約10年ぶりに北海道の留萌ダムに従事することになりました。10年ぶりのダム工事で初めて着手から係わるということで、随分張り切って乗り込んだ記憶があります。
留萌市は北海道の日本海側にあり、『かずのこ』の生産量日本一の町です。また北海道は海の幸が大変美味しく、温泉や名所が数々ありました。昨年は、盆休み等を利用して追い込みであちらこちらの名所をめぐってきました。日本最東端の納沙布岬や知床峠から北方領土の国後島を間近に見たときは、感無量でした。納沙布岬に行った時はGWでしたが、風が強く、寒かったことを覚えています。
三現場合わせて約15年、ダム工事を経験しました。定年後、これらのダムをもう一度見て回ってみたいと思っています。
最後に、昨年の政権交代後、「コンクリートから人へ」という新政権の政策の下、社会資本整備の予算がさらに削減されようとし、ダムに対する風当たりも益々強くなってきています。地球温暖化が世界中で心配されている今日、我々は数十年後を見据えた安心できる国作りのため、手遅れになることがないようダムの重要性や貢献度をアピールしていかなければならないと感じています。
(だよりN0.44号:会員の輪より抜粋)
| ■前のページへ■ ■次のページへ■ |